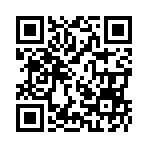11月18日(土)活動
2023年11月21日
2023/11/18(土) 滋賀LD教育研究会(S.E.N.Sの会滋賀支部会)定例研究会 15:30~
参加メンバー:10名
自己紹介
1.報告
チャレンジクラブ 参加者4名
「ちょっと早いクリスマスケーキのデコレーションをしよう」
前回からの予定。こどもたちは期待していた。やる気満々。昨年はチョコフォンデュ(チョコを溶かして果物にチョコをつけて食べる)。
◎調理の経験もあり、イメージし易かった。
◎うれしそうな表情が見られた。
◎互いに声をかけ会う、手助けをする場面もあった。(シャンメリーの瓶の蓋がなかなか開けられなかった時など)
◎少しずつ他者との関係を作っていった子もいる。
◎フルーツを切る→縦・横などの工夫。
◎欲しい物があった時、先生に「取ってきて」→自分で言ったらいいよ→お願いします→涌嶋先生にもらってくる→ありがとうございます。などていねいな言葉遣いでお願いが出来た。
◎ケーキ作りが初めてだった子ども→先生に褒められうれしそうな表情→みんなの前で発表出来た。
◎他の子を褒めて雰囲気を盛り上げてくれた子もいた。
◎名札がつけられなかった子→先生から促されしばらくしてから自分でエプロンにつけていた
保護者向け研集会 7名、チャレンジクラブ参加の子どもの担任の先生がオンライン参加
◎知徳体がバランスよく育つことが豊かな生活につながると考えられるが、バランスが取れずしんどさを感じる子どもがいる。
◎どんな配慮が必要だろうか
◎配慮の一つとしてICTがある。国もその整備を進めている。
2.情報交換(お悩みや相談など)
Q.通級指導教室で、読み書きのしんどい子への指導について
「3年生の今の段階で、進路を見越してどんな指導が効果的でしょうか。」
◎読み書きについて専門的に研究されているのは大阪医科薬科大学のLDセンター奧村先生かな。
◎東京大学 先端科学技術研究センターの近藤武夫先生も詳しく研究されている。
◎こういうところから読み書きの指導について情報を集めてみてはどうか。
◎読み書きのしんどさがあること=人より劣っているではない。自分の価値はどこにあるのかを考える。いっしょに考える。
◎通級指導教室では、しんどい思いをしてきている子が来ているので、小学校・中学校では「どんな自分になりたいか」を考えられるようになって欲しいと思っている。
◎他の人と比べるのではなく、自分自身を見つけること。そのために子どもたちにどんな方向から近づいて行けばいいかを工夫しながら考えている。子ども一人ひとりで近づき方は異なってくる。その子の「好き」から近づくのが近道ではないか。
◎自分の苦手な所はツールを使って補おうとする。音声ペン、音声入力、音声読み上げ(肉声・電子音声)、拡大文字などいろいろなツールがある。自分で何とかしようという気持ちになれるように育てていく。

参加メンバー:10名
自己紹介
1.報告
チャレンジクラブ 参加者4名
「ちょっと早いクリスマスケーキのデコレーションをしよう」
前回からの予定。こどもたちは期待していた。やる気満々。昨年はチョコフォンデュ(チョコを溶かして果物にチョコをつけて食べる)。
◎調理の経験もあり、イメージし易かった。
◎うれしそうな表情が見られた。
◎互いに声をかけ会う、手助けをする場面もあった。(シャンメリーの瓶の蓋がなかなか開けられなかった時など)
◎少しずつ他者との関係を作っていった子もいる。
◎フルーツを切る→縦・横などの工夫。
◎欲しい物があった時、先生に「取ってきて」→自分で言ったらいいよ→お願いします→涌嶋先生にもらってくる→ありがとうございます。などていねいな言葉遣いでお願いが出来た。
◎ケーキ作りが初めてだった子ども→先生に褒められうれしそうな表情→みんなの前で発表出来た。
◎他の子を褒めて雰囲気を盛り上げてくれた子もいた。
◎名札がつけられなかった子→先生から促されしばらくしてから自分でエプロンにつけていた
保護者向け研集会 7名、チャレンジクラブ参加の子どもの担任の先生がオンライン参加
◎知徳体がバランスよく育つことが豊かな生活につながると考えられるが、バランスが取れずしんどさを感じる子どもがいる。
◎どんな配慮が必要だろうか
◎配慮の一つとしてICTがある。国もその整備を進めている。
2.情報交換(お悩みや相談など)
Q.通級指導教室で、読み書きのしんどい子への指導について
「3年生の今の段階で、進路を見越してどんな指導が効果的でしょうか。」
◎読み書きについて専門的に研究されているのは大阪医科薬科大学のLDセンター奧村先生かな。
◎東京大学 先端科学技術研究センターの近藤武夫先生も詳しく研究されている。
◎こういうところから読み書きの指導について情報を集めてみてはどうか。
◎読み書きのしんどさがあること=人より劣っているではない。自分の価値はどこにあるのかを考える。いっしょに考える。
◎通級指導教室では、しんどい思いをしてきている子が来ているので、小学校・中学校では「どんな自分になりたいか」を考えられるようになって欲しいと思っている。
◎他の人と比べるのではなく、自分自身を見つけること。そのために子どもたちにどんな方向から近づいて行けばいいかを工夫しながら考えている。子ども一人ひとりで近づき方は異なってくる。その子の「好き」から近づくのが近道ではないか。
◎自分の苦手な所はツールを使って補おうとする。音声ペン、音声入力、音声読み上げ(肉声・電子音声)、拡大文字などいろいろなツールがある。自分で何とかしようという気持ちになれるように育てていく。

次回、11/18(土)の活動
2023年11月03日
しばらく暖かな日が続きます。
先日の満月も美しかったです。
明け方にはオリオン座の三つ星が鮮やかに見られるようになり、ますます秋の深まりを感じます。
さて、次回の活動です。
11月18日(土) 対面+Zoom
チャレンジクラブ(簡単な調理)・保護者向け研修会(同時進行)
終わり次第定例研究会
場所 G-NETしが【周辺地図・アクセス】https://www.pref.shiga.lg.jp/g-net/about/103674.html
滋賀県立男女共同参画センター“G-NETしが”
〒523-0891 滋賀県近江八幡市鷹飼町80-4
TEL 0748(37)3751 / FAX 0748(37)5770
場所
調理実習室:チャレンジクラブ
研修室C :研修会
日程
14:00~チャレンジクラブ打ち合わせ (担当:澤居先生、磯田先生)
14:30~チャレンジクラブ&保護者向け研修会(対面+Zoom)
保護者向け研修会のテーマ
「学習支援(配慮)。従来の固定した考え方からの脱却へ ~特性への「気づき」と「理解」、そして「支援」へ~
担当:久郷会長
15:30~定例研究会(対面+Zoom)
内容:チャレンジクラブ・保護者向け研修会の報告、情報交換やお悩みなど、2024年1月13日(土)S.E.N.Sレベル研集会について
担当:事務局(山田、小島)
会員の方でまだ参加されていない方、一度参加しませんか。
前回の活動も始めての方に参加していただきました。
いろんな方に参加していただき、いろんなお話ができればと思います。
では、気温差が大きな時期ですのでお身体には充分お気をつけください。

先日の満月も美しかったです。
明け方にはオリオン座の三つ星が鮮やかに見られるようになり、ますます秋の深まりを感じます。
さて、次回の活動です。
11月18日(土) 対面+Zoom
チャレンジクラブ(簡単な調理)・保護者向け研修会(同時進行)
終わり次第定例研究会
場所 G-NETしが【周辺地図・アクセス】https://www.pref.shiga.lg.jp/g-net/about/103674.html
滋賀県立男女共同参画センター“G-NETしが”
〒523-0891 滋賀県近江八幡市鷹飼町80-4
TEL 0748(37)3751 / FAX 0748(37)5770
場所
調理実習室:チャレンジクラブ
研修室C :研修会
日程
14:00~チャレンジクラブ打ち合わせ (担当:澤居先生、磯田先生)
14:30~チャレンジクラブ&保護者向け研修会(対面+Zoom)
保護者向け研修会のテーマ
「学習支援(配慮)。従来の固定した考え方からの脱却へ ~特性への「気づき」と「理解」、そして「支援」へ~
担当:久郷会長
15:30~定例研究会(対面+Zoom)
内容:チャレンジクラブ・保護者向け研修会の報告、情報交換やお悩みなど、2024年1月13日(土)S.E.N.Sレベル研集会について
担当:事務局(山田、小島)
会員の方でまだ参加されていない方、一度参加しませんか。
前回の活動も始めての方に参加していただきました。
いろんな方に参加していただき、いろんなお話ができればと思います。
では、気温差が大きな時期ですのでお身体には充分お気をつけください。

怒りへの対処
2018年02月06日
10月21日付け「保護者研修会」の続編 part2 です。(小西喜朗先生による保護者向け研修会より)
「怒りへの対処」についてです。
〇「衝動性」にどう対処するか
「6秒間ルール」=アドレナリンはすぐに消える。
「怒りが持続する」は6秒間が持続するということ。
「ガマン」でなく、気持ちを別の方向に向ける練習をする。
〇「考え方」を変えてみる
「怒りの正体」=自分の「べき」から外れたときの気持ち
「べき」=自分は当たり前だと思っている強い思い込み=絶対正しい
〇「べき」を和らげる練習
違う考え方を受け入れる練習
「べき」を押し付けない練習
気持ちを落ち着けて自分の考えを伝える練習
〇上手に怒るために
怒るときの基準は「内容」。その時の気分ではない。
言いたいことを一つに絞る。
原因さがしはしない。→言い訳につながる
事実をきちんと捉え、相手の考えを聞く。
〇怒りの後の行動を自分で決める
状況を見極める
1 できる 変えられる→いつまでに どうやって どのくらい
2 できない 変えられない→代わりにできること 放っておくことができるか
今回はここまでです。
次回はもう少し具体的に、「衝動的に怒らないようにしよう」を載せたいと思います。
「怒りへの対処」についてです。
〇「衝動性」にどう対処するか
「6秒間ルール」=アドレナリンはすぐに消える。
「怒りが持続する」は6秒間が持続するということ。
「ガマン」でなく、気持ちを別の方向に向ける練習をする。
〇「考え方」を変えてみる
「怒りの正体」=自分の「べき」から外れたときの気持ち
「べき」=自分は当たり前だと思っている強い思い込み=絶対正しい
〇「べき」を和らげる練習
違う考え方を受け入れる練習
「べき」を押し付けない練習
気持ちを落ち着けて自分の考えを伝える練習
〇上手に怒るために
怒るときの基準は「内容」。その時の気分ではない。
言いたいことを一つに絞る。
原因さがしはしない。→言い訳につながる
事実をきちんと捉え、相手の考えを聞く。
〇怒りの後の行動を自分で決める
状況を見極める
1 できる 変えられる→いつまでに どうやって どのくらい
2 できない 変えられない→代わりにできること 放っておくことができるか
今回はここまでです。
次回はもう少し具体的に、「衝動的に怒らないようにしよう」を載せたいと思います。
保護者向け研修会
2017年10月23日
10月21日(土)保護者向け研修会
アンガーマネジメント 〜怒りをコントロールする〜 小西喜朗(こにし よしお) 甲南中部小学校長
<第1部>「怒り」について
〇「怒り」の気持ちとはなにか
1.「怒り」の気持ちは大切な物。
2.「怒り」を認める。=必ず理由がある。
3.「怒り」はコントロールできる。=「怒りの表し方」は自分が選べる。
〇「怒り」=悪ではない。抑えると不満がたまる。
〇「怒り」=自分を守るためのものである。
〇「怒り」の状態
1.「怒りの頻度」→伝染する
2.「怒りの持続」→恨み、にくしみへと変わって引きずる
3.「強度が高い」強く怒る→誰も近寄らない
4.「攻撃性がある」怒り→解決しない。「相手を傷つけない、自分を傷つけない、モノに当たらない。」が大切なルール
〇「怒り」の性質
1.二次感情=つらい、悲しい、寂しい(一次感情)→徐々にたまって「怒り」へ
2.爆発する=いろいろな感情のかたまり→「怒り」の中にある本等の気持ちに寄り添えると爆発はしない
3.連鎖する=強い者から弱い者へ流れる 連鎖を断ち切る
〇「怒り」の仕組み
1.できごと(イスがぶつかった)
2.できごとについて考える(わざとじゃないのか?)(痛かったけど、わざとじゃない)
3.考え方が決まる
4.「怒り」が生まれる「いらっ」とする=「怒り」が生まれる まっいいか=「怒り」が生まれない
できごとが同じでも、考え方が変わると「怒り」が生まれない
〇「怒り」のサイクル
1.できごと
2.できごとについて考える 【考え方を変えてみる】
3.考え方が決まる
4.「怒り」が生まれる
5.行動する 【行動を変えてみる】
6.行動の結果
7.じぶんの中にある考え方に影響する
<第2部>「怒り」への対処を次回に載せます。
アンガーマネジメント 〜怒りをコントロールする〜 小西喜朗(こにし よしお) 甲南中部小学校長
<第1部>「怒り」について
〇「怒り」の気持ちとはなにか
1.「怒り」の気持ちは大切な物。
2.「怒り」を認める。=必ず理由がある。
3.「怒り」はコントロールできる。=「怒りの表し方」は自分が選べる。
〇「怒り」=悪ではない。抑えると不満がたまる。
〇「怒り」=自分を守るためのものである。
〇「怒り」の状態
1.「怒りの頻度」→伝染する
2.「怒りの持続」→恨み、にくしみへと変わって引きずる
3.「強度が高い」強く怒る→誰も近寄らない
4.「攻撃性がある」怒り→解決しない。「相手を傷つけない、自分を傷つけない、モノに当たらない。」が大切なルール
〇「怒り」の性質
1.二次感情=つらい、悲しい、寂しい(一次感情)→徐々にたまって「怒り」へ
2.爆発する=いろいろな感情のかたまり→「怒り」の中にある本等の気持ちに寄り添えると爆発はしない
3.連鎖する=強い者から弱い者へ流れる 連鎖を断ち切る
〇「怒り」の仕組み
1.できごと(イスがぶつかった)
2.できごとについて考える(わざとじゃないのか?)(痛かったけど、わざとじゃない)
3.考え方が決まる
4.「怒り」が生まれる「いらっ」とする=「怒り」が生まれる まっいいか=「怒り」が生まれない
できごとが同じでも、考え方が変わると「怒り」が生まれない
〇「怒り」のサイクル
1.できごと
2.できごとについて考える 【考え方を変えてみる】
3.考え方が決まる
4.「怒り」が生まれる
5.行動する 【行動を変えてみる】
6.行動の結果
7.じぶんの中にある考え方に影響する
<第2部>「怒り」への対処を次回に載せます。