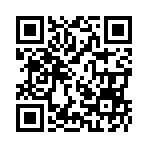北脇ゼミ2020年7月18日(土)
2020年12月01日
今回は、実践的コミュニティーについて
北脇先生が巡回された校内研究の様子から気づいたことを中心にお話しいただきました。
1今回のテーマについて
①きっかけになったのは
②私の原体験
③実践交流が具備すべき要件
2学校現場の実践を深めるために
①当事者研究として位置付ける
②学校現場の取り組みを振り返って
③校内研究の進め方
④研究紀要にまとめる意味
⑤インフォーマルな取り組み
意見交換では
〇現場教員の学びは?
〇校内研究の在り方は?
〇いじめ問題の取り組みは?
〇特別支援教育の推進方策は?
という話題が出ました。
以下にまとめを載せました。
ご興味ある部分からお読みいただければと思います。



















以上です。
いかがでしたか。
ご感想やご意見は下記のメールアドレスまでお寄せ下さい。

kitawakisemi@gmail.com
北脇先生が巡回された校内研究の様子から気づいたことを中心にお話しいただきました。
1今回のテーマについて
①きっかけになったのは
②私の原体験
③実践交流が具備すべき要件
2学校現場の実践を深めるために
①当事者研究として位置付ける
②学校現場の取り組みを振り返って
③校内研究の進め方
④研究紀要にまとめる意味
⑤インフォーマルな取り組み
意見交換では
〇現場教員の学びは?
〇校内研究の在り方は?
〇いじめ問題の取り組みは?
〇特別支援教育の推進方策は?
という話題が出ました。
以下にまとめを載せました。
ご興味ある部分からお読みいただければと思います。



















以上です。
いかがでしたか。
ご感想やご意見は下記のメールアドレスまでお寄せ下さい。

kitawakisemi@gmail.com
北脇ゼミのお知らせ
2020年07月05日
北脇ゼミの記録
2019年10月09日
第8講 3回目
2019年9月21日(土) 北脇ゼミ 記録
特別支援教育の教育学的吟味Ⅰ
苫野一徳氏の論考をもとに
はじめに
特別支援教育は通級指導教室が先導した。対象になる子どもの医学的診断や心理学的諸検査を実施して弱点部を明らかにし、その改善に取り組んだ。つまり医学・心理学的治療モデルがベースになっている。特別支援教育を教育学の立場から見つめ直す必要があるのではないかと、私はかねてから考えていた。
それには背景があった。30数年も前のことであるが、関西教育学会(1983年)のシンポジウムで、わたしは「生活主義に立った障害児教育の推進」を主張した。京都大学の田中昌人氏から、「生活を教育に持ち込むにあたっての教育学的な吟味はあるのか」との問いかけがあった。その頃のわたしは、生活主義に立った障害児教育は当然のことだと考えていたので、驚きであった。本当に彼らへの教育としてふさわしいものなのかと、自分への問いかけが、それ以後続いていた。
手がかりになるものがわからないままでいたところ、苫野一徳氏の本に出会った。「学校をつくり直す」や「はじめての哲学的思考」などの論考をもとにすれば、長年の懸案事項たった特別支援教育を教育学的に吟味できるのではないかと考えるようになった。
今回を初めとして、あと2・3回、このテーマでゼミを開くこととした。
1 望ましい教育システムとはなにか
苫野一徳氏は、
「現代の教育システムは、みんなが同じことを同じペースで、できあいの内容を一斉に学習する。それはもう限界。ふきこぼれ…わかっているのにお付き合いしなければならず、やる気をなくしている子や落ちこぼれの子が多く出ている。楽しく生き生きと学ぶことになっていない。新しい教育システムを構築する必要があるのではないか」と主張している。
特別支援教育は、この教育システムには乗れなかった。みんなが同じことを同じペースで、できあいの内容を一斉に学習することなどは考えられなかった。そこで、特殊教育という特別枠を設けた。そのとき、モデルになったのは幼児教育である。
苫野さんも新たな教育システムのベースにおくのは幼児教育だと考えている。ルソーやモンテッソーリの教育を引用して、主体性をもって日々送っていることを主眼にした。
しかし、幼児教育で育てた主体性が小学校に入学すると教科別一斉指導の中で押し潰されている。1年生プロブレムとなって表れている。
では、幼児教育の次の段階はどのように繋いでいくべきか。イエナプラン、ドルトン教育、シュタイナー教育などの自由教育の実践が位置付くと苫野さんは考えている。
特殊教育では。教科別指導ではなく、領域・教科を合わせた学習が中核を占める。生活単元学習や作業学習である。その元はドルトン教育にあった。
1985年5月、わたしは横浜市立大学・伊藤隆二先生主宰の「ヨーロッパ自由教育・障害児教育の源流を訪ねる」というツアーに参加し、その一端にふれるとができた。
オルタナティブ(自由選択)教育を進めているシュタイナー学校や、サマーヒル学園、フレネ学校などを参観した。フレネ学校の日々の教育プログラムには、自由作文がある。登校の風景などを作文する。
その作文が黒板に書かれ、クラスのみんなで文法上の誤りや表現方法を検討している。やり終えると、この作文は活字をひらって印刷する。アルファベットの活字を拾い、手フード機で一枚、一枚と印刷していく。ある程度、作文が溜まるとⅠ冊にまとめて教科書にする。子どもの学びが教科書になる。この教科書は、同じ系列の学校で交換し合う。子どもの見聞きする世界は限定されているから、この教科書の交換は、子どもたちにとって新たな刺激になる。見学者がやってくると、その教科書を販売する。ここでの売り上げは学校協同組合で管理され、学習活動の資金として活用される。
苫野さんはこういうのをイメージしているのではないか。
2 新たな教育システムの構築に当たって
5・6年前、アクティブラーニングがやかましく語られ出した。そのとき、ある幼稚園の園長さんは、「今さらなにを言うのか。幼稚園の自由遊びは、それをやっているではないか」とおっしゃった。
苫野さんは、アクティブラーニングを単に協同的な話し合いの場を設ければいいのではないかと受け止められている現状を批判し、
学びの個別化・協同化・プロジェクト化
を新たな教育システムの中核にと主張している。
〇〇スタンダードという流行がある。授業や生活に、そのやり方を示し、順守させれば一定の成果が上がると、教育委員会などが主導している。これは、行政や学校管理には都合がいいだけではないか。多様化の尊重や個に応じた指導などに逆行している。新たな教育システムは、学びの個別化・協同化・プロジェクト化をめざすが、これはスタンダード化を図ることではない。
特別支援教育でも、スタンダードを作っているのではないか。「これなら上手くいく」と考えていないだろうか。
わたしはADHDの指導では、
① 焦点化する。
② 作業化する。プリントを書くなどの作業を多く取り入れる
➂ 見通しを持たせる。どこまでやったら終わりかを明示する、
などでADHD児も集中できると原理化している。これは、それなりの成果があがる。しかし、細かくやり方が決められ、スタンダード化が図られたら、どうなるか。原理は、対象に合わせて変化してこそ、成果が得られる。どこでもだれでもに通用するようなスタンダードなどはあり得ないのではないか。
新たな教育システムの妥当性の検証は、この立ち位置からなされねばならない。そうなってこそ教育改革に向かうことができる。
特別支援教育の推進において、コーディネーターの任命、支援委員会の設置、個別の指導計画の作成などといった施策がとられているが、これらは、どのような原理が働けばよいのかといった検証が必要だと考えている。
苫野氏は「EBPM ( Evidence Based plan Making:証拠に基づいた施策化)には、哲学と教育学のセンス」が必要だとも言っている。
科学が導き出すのはあくまでも仮説的な事実であり、そこから当為(すべし)を直接得ることはできない。哲学は、本質を観取して、その意味を明らかにする。両者の融合が必要だと。
LDのひとの社会自立の力とは何か。どう付き合えばいいのか。吃音でも同じ。そのままで十分社会生活が送れるやり方を手に入れれば、生活が豊かになる。吃音を直すことが全てではない。
公教育の本質とは、「自由の相互承認」の態度を育むこと。自分として、障害は障害として受け止め、生きていくための「力」を育むこと。
これまでの教育はここが曖昧であった。特別支援教育がインクルーシブ教育として進展しているが、自分自身の力を最大限に発揮できる力を育む方向へと学校マネージメントを実施しなければならない。
問われているのは?
① 現代において「自由」に生きるための力とは何か?
② その力はどうすれば育めるのか
③「自由の相互承認」の感度はどうすれば育めるのか?
その一翼を担うのが学びの個別化・協同化・プロジェクト化。探求型の学習である。自分たちなりの問いを立て、自分たちなりの仕方で、自分たちなりの答えにたどり着く。
附属中学校のびわこ学習が、それに相当する。学年を解体してテーマごとにグループを作り、探求型の学習を長年実施している。これは、かって附属中学校のD組の行っていた「生活単元学習びわこ」が原型ではないかと、私はひそかに思っている。
探求型の学習では、教師は、共同研究者である。ある幼稚園で「土に埋めた氷は厚くなる」と言った子がいた。実際に埋めたら氷は溶けていた。その子はみんなから責められ、「なんで?」と先生に訴えた。しかし、担任はすぐに答えを出さなかった。
T「どうしてだろうね。」
CH「前は太くなったのに!」
T「前はどこに埋めたの?」
とヒントを積み重ね、木陰に埋めたことがわかる。いつ掘り返したのか?朝に掘り返した。今と違うよね。先生の問いかけで考えを深めていく子どもたちの姿があった。
デューイの考え方。Learning by doing:為すことで学びが広がる。
テーマに浸りきる。探求テーマに対する問いを立てる。方法を考え、実施。発表する。
[よく遊ぶ子はよく学ぶ子になる]と言われるが、幼稚園の先生たちは、本当に遊びに浸る子は,、小学校に入ってもよく学ぶ子になるのかどうか確信が持てなかった。幼稚園と小中との話し合いが幾度っもたれた。学びは、わくわくすること。探求は最高の遊び。遊びと学習は連続していると考えられるようになった。これが探求型の学習である。
今回のゼミでは苫野氏の論考をもとに、特別支援教育を吟味する二つの切り口が得られた。
一つ目は「望ましい教育システムはなにか」:現在の特別支援教育は,障害のある子もそうでない子もが共に学び合える望ましい教育システムと言えるかどうかを吟味することである。
二つ目は、「新たな教育システムの構築に当たって」吟味すべき課題をとり上げた。次回以降では、この切り口からの考察を進めたいと思っている。
<研究協議>
(1)特別支援教育と通常の教育は融合できるか
中学校の中においては、特別支援学級と通常学級では、あきらかに価値観が違っている。はたして、この両者は、一つの教育システムとして存在できるのか。どのように考えていけばいいのだろうか。
インクルーシブ教育は「包括する」という意味です。特別支援教育を通常教育の中に含めていくという考え方ですね。わたしは、この考え方をもう一歩進めて、特別支援教育が通常教育を包括するものと逆に考えることが、今日的な解釈ではないか。この考えは、支援学級と通常学級が別枠で存在するという教育システムの組織からではなく、特別支援教育の機能(どのような困難さがあろうが、その子の生活や学習を保障していく)から見ていけば、その機能を通常教育にも持ち込まねばならないわけですから、当然通常教育は特別支援教育に包括されねばならないわけです。今はまだまだ通常教育は、特別支援教育機能の圏外にいる。もっと中に収まるように考えていく。現実的には一気にフレネ学校のようにはならないから、部分的に行っていく。成就感、達成感がある教育の体験を増やす。総合的学習を根っこにおいた探求型のプロジェクトを組織して、徐々に広げていく。教科の学習においても、探究型学習をどのように位置づけていくのか、これから考えていくべきではないか。
探求型学習の例として、苫野氏は島根県隠岐の島の島前(どうぜん)高校が、地域課題である過疎化を食い止めるため、全国から生徒が来る高校作りをしていることをとり上げている。これによって、学校も地域も活性化させている。
また、京都の堀川高校は教え込みではなく、大学の研究のような授業をしていた。堀川の奇跡として話題になった。
一方、総合的学習が陳腐になってしまって、形骸化しているところもある。総合的学習にどう取り組むかがわからない教師が出てきて、スタート時は探求型の学習(たんけん・はっけん。ほっとけんが合い言葉だった)であったが、だんだんとないがしろになってしまった。
(2)総合的学習がないがしろにされたのはなぜか
学力を測定可能な基礎学力を中心に検査するようになって、一気に総合的な学習がだめになった。また、総合的な学習は家庭の文化度や家庭の学力がベースになる。この面で優位の子は力を出せるが、ベースが弱い子にとっては総合的学習は何をするのかわからないということから、格差が生じた。しかし、熱心に取り組んできた長野県や岐阜県では、現在もがんばってやっている。
幼児期における遊びは、総合的な学習そのものである。その延長線上で小・中学校の総合的学習をやっていけば、格差は現れないのではないか。探究型の学習をやっていないところで、格差が生じているのではないか。
現在、幼稚園より認定こども園が多くなってきた。そうすると、従来の幼稚園教育が担ってきた自由遊びの中での主体的で対話的な深い学びが、保育園の「預かり保育」に変化してきているのではないか。また、障害のある子どもへの支援加配員がつくようになって、その子の面倒を見る役割になったことから、障害のある子を含む友だち同士の対話的な深い学びがなくなってきている。加配の在り方をもっと論議しないと、幼稚園の統合保育がインクルーシブ教育の在り方の追求に結びつかない。おそれがある。
(3)子ども一人ひとりの深い学びを、どのように見取るか
先日、授業研究会があった。「深い学びをどう仕組むか」が課題であった。理科の授業では、生徒は4人のグループで滑車を転がして、記録用紙を見ながら読み取る力を育てる授業だった。具体物で試行錯誤しながら意見を出し合っていくという流れであった。
このような探求型の学習では、できた子、できなかった子、きっかけのなかった子などに、どのように寄り添っていけばよいのか。「もうちょっとこうやってほしいな」と思う子どももいた。いつも授業中寝ている子が4人のグループでは、少し顔を上げてまとめを書いていた。すごく頑張った姿であったと思うが、全員の中では、評価されなかった。これまでの一斉授業とは違って、探究型の授業では、一人ひとり子どもへの見方をもっていないと授業にならない。一人ひとりの子どもの姿を見ていないと評価できていない。はたしてこの見つめ方を教師がどれだけ持てているのか。
粟津中学校の学び合いの研究協議では、先ほどのような子どもの表情の細かな動きを注目した発言をするように指導され、先生方から子どもの表情についての意見が多く出るようになった。アドバイザーが子どもの表情の見方やその子の学びの読み取り方を示してくれる。そういう存在が必要なのかも知れないと感じる。
幼稚園の先生方は、その子の成長を見守る見方をしている。どのように見守るかは、まだまだ過渡期であり、園の中で調整中である。
通常学級の中の探求型の学習では、どれだけ深い学びをしているのかを的確につかめるかどうかが大きな課題となる。。深い学びは外に現れにくい。長い経過の中で見続けていって、どのような学びを獲得したかを検証しなければならない。前の単元でやっていたことが次の多安元で、このように現れたのかを、実際に体験したことがある。一人一人の子どもが、どのように変わってきたのかが見つめられないと深い学びは捉えられない。その子の知識技能の高まりだけでは、深い学びだったかどうかは判断できないのではないか。
授業参観では、みんな一生懸命やっていると感じたが、これまでの一斉授業の中で身に着けた学習スタイルがどれだけ変化したのか。なにをさして深い学びと言えるのかとなると難しい。
・できあいの答えに到達することではない。
・答えをすぐに言ってほしい子もたくさんいる。
・自分が更なる問いをたくさん持つ子もいる。
・本当に自分が知りたかった内容が明確になった子もいる。
明治以降の教育は、一定の内容を効率的に教えることであった。深い学びというのは、そのような学習内容の効率的な習得ではない
ハーバード大学のサンディ教授の授業をNHKで見たことがある。サンディ教授は、参加者の一人の前の発言を覚えていて、「今の発言との関係はどうであったのか」と指摘している。その参加者に深い学びを意識させようとしている。一斉授業の中でも深い学びを行うこともあったのではないか。
以前、林竹二先生(宮城教育大の学長を務められた方)の授業を見たことがある。これはほとんど子どもたちとのやり取りはなく、大学の講義のようだった。しかし、授業の後で、子どもたちが書いた作文を見ると、一人一人が深い深い学びをしている。林竹二先生は、子ども一人一人の内面に語りかけていたのだ。そうでなければ、あれほどの作文が書けるはずがない。「自分はソクラテスの問答法で授業をやっている」と、先生は述べているが、わたしなどが真似られるものではなかった。子どもの内面をしっかりつかむ方法と技術を身につけねばならない。
(4)今後、深めたい内容
今回のゼミでは、特別支援教育を教育学的に吟味する二つの切り口、
1 どの子にとっても、望ましい教育システムとはなにか
2 新たな教育システムを構築するには
を提言した。
これを受けての研究協議では、
1 特別支援教育と通常の教育は融合できるのか
2 総合的学習がないがしろにされたのはなぜか
3 子ども一人ひとりの深い学びを、どのように見取るか
と、この切り口から深めなければならない内容が提案された。
今後深めたい内容は、これらがベースになると考えている。
1) [特別支援教育の進展過程に見られる通常教育との関連]を、まず明らかにしていきたい。
わたしは、1960年代に小学校の特殊学級の担任した。職場が変わっても、この教育に携わり続けた。一時、養護学校に勤務したが、小中学校特殊学級が組織する県特殊教育研究会の会長を務めるなど、小中学校の特殊教育に関わっていた。
特殊教育は最初、通常学級では学べない異常児の教育して、通常の教育とは別枠で進められた。その後、特殊教育は障害児教育へと進み、特別支援教育の時代を迎えた。この進展過程で、特殊教育は通常の教育とどのように関係していたのか。ここを明らかにすることで、「1 特別支援教育と通常の教育は融合できるのか」に答えられるのではないか。
2)つぎに考察したいのが、「インクルーシブ教育の推進課題」である。
文部科学省は、インクルーシブ教育の推進に当たって、特別支援教育を大きく位置付けている。しかしながら学校現場では、研究協議で指摘された「2 総合的学習がないがしろにされたのはなぜか」を踏まえて、この振興方法を考えねばならない。障害のある子と、そうでない子が共に学ぶインクルーシブ教育では、総合的学習や特別教育活動がその中核を占めねばならないと考えるからである。
3)校内研究・研修の見直し
特別支援教育の教育学的吟味において、これは欠かすことができない課題だと思っている。研究協議で出された、「3 子ども一人ひとりの深い学びを、どのように見取るか」は、校内研究・研修でとり上げねばならない課題である。
また、ここでは、
・ 従来の授業研究を中心とした校内研究でよいのかも検討されねばならない。
・ 個別の指導計画の見直し
日々の実践の中で立案し、実施し教育するのか。今の指導計画では欠陥部分を書き上げ、そこへの指導目標を書くようになっている。自分の長所をどう生かすのか、どう生きるのが一番いいのかを考える指導計画が必要だと思う。自己理解と他者理解する力を育てるにはどうすべきか、などが考察すべき対象になる。
4)最後にLD研で話したように、特別支援教育を中核においた学校マネージメントを究明したい。
文科省のHPを見ると、「共生教育の方向」、「学校の重点目標」、「前年度の学校経営評価をどうするか」などが掲載されている。インクルーシブ教育をどのように進めていくかの学校マネージメントの考察である。
5)今後の展望のために出された意見
〇新学習指導要領は現状の追認をしている。通常学級の中には発達障がい児や、日本語が話せない外国籍の子、義務教育の未終了の子がいる。これらを認めている学習指導要領になっている。そういう子らをまとめてみていく教育でないとやっていけないと考えている。同じ質の子、できあいの答えの教育ではなくなっている。教育のスタンスはかわっている。次の10年後の指導要領では、学年の縛りがゆるくなるだろう。新しい教育システムの構築では、学年の縛りを取っ払う必要がある。
しかし 新学習指導要領が現場では、どれだけ意識されているか。まだまだの状況ではないか。ある市では、いまようやく授業改善が行われ出した。授業研究では、この授業の中に外国籍の子がいる、発達障害の子がいることが話題にはならない。学習指導要領が改正されても、その趣旨を知らないままの人がまだまだ多いのではないか。管理職も学校課題がいっぱいある中で、なにを選択し、なにを伝えるのかハッキリしていない。文科省の考えが浸透するには時間がかかる。
変化には時間がかかるが、インクルーシブの考え方は全世界的な流れである。少しずつ変わっていくのではないか。学年別教科教育にどうしたら特別支援教育が融合できるか。ではなく、特別支援教育をベースにした通常教育を考えないといけない。探求型の学習組織へと学校が変わらないといけないのではないだろうか。
壁になるのは学力テストやいじめの問題である。「友だちを叩いたらいじめである」とはじき出すようなことをしながら、一方ではインクルーシブ教育と言っている。また、学力が足りない人を切り取り、みんなと一緒に学ぶのではなく、個別に教える対象にしている。
以上のような学校現場の状況を踏まえつつ、特別支援教育をベースにした、新しい教育システムの在り方が問われている。
〇いじめや友達同士での激しいやり取りを経験して子どもは成長する。そこが保障されないといけない。現場はまったく進んでいないわけではない。カリキュラムは進んできた。校内のマネージメントも言われて来た。しかし、それらを1本にして、新たな教育システムを構築するという動きにはなっていない。ここにメスを入れねばと思う。
では、これらを重点的にどう取り組めばよいか。学校経営方針。それを立案、協議する方法が学校内で考えられていない。学校が一つのチームとして、切磋琢磨する流れにならない。どの時期からスタートして、年度初めに提示するにはいつから協議するのかなどが大きな課題である。1学期の終わりくらいから来年度の方針を検討している学校がある。わたしは校長の時に、年度末の学校評価の時期に、200字で自分のやりたいことを表現してほしいと、「200字提言」を求めたことがあった。その内容を校務分掌を中心に分担して、考えてもらった。
〇学校評価は、どのようになされているのか。ここにもメスを入れねばならない。中学校で、教科指導だけで校長になった人の中には、支援学級のことを知らなかったり、わからない方がいる。生活単元学習の内容や成長の姿を知らないでいる。わたしは支援学級の担任として、いかに支援学級の素晴らしさを他の先生に伝えるかが使命であると教えられたが、まだまだ知ってもらっていないと感じている。30代の先生、支援学級は経験していない。小中高校にも支援学級がなかった先生もいる。こんなふうにそれぞれの先生には背景があり、その先生の考えが成り立っているわけだから、共通理解をすると言っても、それは大変なことである。
〇「はじめての哲学的思考」の中で、苫野一徳氏は、わが校の教育課題は何かと考えるとき、それぞれの信念がある。信念のレベルで話し合ってもかみ合わない。それぞれの信念はどこから生まれているのかを見つめていかないと議論はかみ合わない。信念の形成には欲望が絡んでいる。その欲望のレベルで議論していけば、なにがベースになってその信念が形成されてきたのかわかり、互いに理解し合える場が得られると述べて居る。このやり方が学校現場は取り入れられるか。
〇点が一つにつながるところが大事ではないか。滋賀県の障害児教育は、同和教育からつながってきたと考えられる。
自由の相互承認。教育はすべての人に自由の相互承認がなされるようにするもの。今はまだ対話が成立しない。相手の言葉を聞く、受け止める。対話と自由の相互承認をどう深めるかから始まるのではないか。
〇通常学級の先生でもきめ細かな指導をしている人がいる。それがそのまま特別支援教育の視点だろう。同和教育でも、子どもを見る視点をもったなら、特別支援教育がベースにならなくても良い。そういう先生がたくさん育つ学校ではいじめや学級崩壊はなくなる。そういう力を育てるにはどうしたらいいのか。良い見方をしている先生から見て学ぶことと巡回相談では伝えている。
〇「本質観取が哲学である」と苫野氏は述べて居る。「教育とはなにか」という問いかけから、「それは子どもの姿に現れてくる」と本質観取したとしよう。そこでは、子ども一人一人がどうやったら豊かな人間関係を作り上げるのかを見つめないと、本質観取にまで行き着いて議論することはできないと思う。
〇大津のいじめへの対応では、どうしてそうなるのかという議論がない。現象面を追いかけている行政の指導であり、それに振り回される学校現場がある。発達障害の子はいじめの標的になりやすい、子どもの価値観が一面的になったときにいじめが起こりやすい、クラスや学校に流れる価値観かも知れない、などのいじめにつながる要因をもっと掘り下げる議論がないと、モグラ叩きしているだけである。インクルーシブ教育が教育の外枠になったらいいのにと思う。
〇教育行政はなにをするのか。それは教育現場の支援者になりきることである。現場が張り切ることをしなければならない。東京都の杉並区ではそういう考えに立って教育行政を進めている。地方教育行政が地方分権の流れのもとに進み、地方独自に解決することになっているが、まだまだ中央集権的な考え方に縋ろうとしている。教育研究所などが中心になって、この地域の今日的課題を掘り起こし、方針を探るなど、各自治体が独自に自分たちの地域の教育を考えていくべきである
あとがき
ゼミの記録に、見出しをつけたり、若干の加除修正を施している中で気づかされたことがあった。それは教育的吟味をしているわたしの立ち位置である。わたしは小学校・中学校の特殊学級の担任であったから、まわりでは通常の教育が進められていた。校内の研究活動や生徒指導などは、通常学級の担任といつも一緒に行なっていた。したがって一つの教育課題に立ち向かうとき、わたしは特殊教育と通常の教育との接点に立たねばならなかった。この立ち位置は、その後、教育研究所や教育委員会に勤務していた時を変わらなかった。教職の最後では小・中学校の校長を勤めたが、特殊教育と通常の教育との接点は「接面」に拡大していた。学校経営を特殊教育の立場から構想するようになっていたからである。
今回のゼミでは、「特別支援教育の教育学的吟味」をテーマとしているが、厳密に言えば、「小・中学校の特別支援教育を通常教育との接面から吟味する」ことになる。このように立ち位置が明らかになることで、焦点化した考察ができるのではないかと思っている。関心のある方は、ぜひゼミに参加し、ご一緒に考察が進められたらと願っています。
次回は11月16日(土曜日)。会場は北脇の自宅マンションの集会室です。
2019年9月21日(土) 北脇ゼミ 記録
特別支援教育の教育学的吟味Ⅰ
苫野一徳氏の論考をもとに
はじめに
特別支援教育は通級指導教室が先導した。対象になる子どもの医学的診断や心理学的諸検査を実施して弱点部を明らかにし、その改善に取り組んだ。つまり医学・心理学的治療モデルがベースになっている。特別支援教育を教育学の立場から見つめ直す必要があるのではないかと、私はかねてから考えていた。
それには背景があった。30数年も前のことであるが、関西教育学会(1983年)のシンポジウムで、わたしは「生活主義に立った障害児教育の推進」を主張した。京都大学の田中昌人氏から、「生活を教育に持ち込むにあたっての教育学的な吟味はあるのか」との問いかけがあった。その頃のわたしは、生活主義に立った障害児教育は当然のことだと考えていたので、驚きであった。本当に彼らへの教育としてふさわしいものなのかと、自分への問いかけが、それ以後続いていた。
手がかりになるものがわからないままでいたところ、苫野一徳氏の本に出会った。「学校をつくり直す」や「はじめての哲学的思考」などの論考をもとにすれば、長年の懸案事項たった特別支援教育を教育学的に吟味できるのではないかと考えるようになった。
今回を初めとして、あと2・3回、このテーマでゼミを開くこととした。
1 望ましい教育システムとはなにか
苫野一徳氏は、
「現代の教育システムは、みんなが同じことを同じペースで、できあいの内容を一斉に学習する。それはもう限界。ふきこぼれ…わかっているのにお付き合いしなければならず、やる気をなくしている子や落ちこぼれの子が多く出ている。楽しく生き生きと学ぶことになっていない。新しい教育システムを構築する必要があるのではないか」と主張している。
特別支援教育は、この教育システムには乗れなかった。みんなが同じことを同じペースで、できあいの内容を一斉に学習することなどは考えられなかった。そこで、特殊教育という特別枠を設けた。そのとき、モデルになったのは幼児教育である。
苫野さんも新たな教育システムのベースにおくのは幼児教育だと考えている。ルソーやモンテッソーリの教育を引用して、主体性をもって日々送っていることを主眼にした。
しかし、幼児教育で育てた主体性が小学校に入学すると教科別一斉指導の中で押し潰されている。1年生プロブレムとなって表れている。
では、幼児教育の次の段階はどのように繋いでいくべきか。イエナプラン、ドルトン教育、シュタイナー教育などの自由教育の実践が位置付くと苫野さんは考えている。
特殊教育では。教科別指導ではなく、領域・教科を合わせた学習が中核を占める。生活単元学習や作業学習である。その元はドルトン教育にあった。
1985年5月、わたしは横浜市立大学・伊藤隆二先生主宰の「ヨーロッパ自由教育・障害児教育の源流を訪ねる」というツアーに参加し、その一端にふれるとができた。
オルタナティブ(自由選択)教育を進めているシュタイナー学校や、サマーヒル学園、フレネ学校などを参観した。フレネ学校の日々の教育プログラムには、自由作文がある。登校の風景などを作文する。
その作文が黒板に書かれ、クラスのみんなで文法上の誤りや表現方法を検討している。やり終えると、この作文は活字をひらって印刷する。アルファベットの活字を拾い、手フード機で一枚、一枚と印刷していく。ある程度、作文が溜まるとⅠ冊にまとめて教科書にする。子どもの学びが教科書になる。この教科書は、同じ系列の学校で交換し合う。子どもの見聞きする世界は限定されているから、この教科書の交換は、子どもたちにとって新たな刺激になる。見学者がやってくると、その教科書を販売する。ここでの売り上げは学校協同組合で管理され、学習活動の資金として活用される。
苫野さんはこういうのをイメージしているのではないか。
2 新たな教育システムの構築に当たって
5・6年前、アクティブラーニングがやかましく語られ出した。そのとき、ある幼稚園の園長さんは、「今さらなにを言うのか。幼稚園の自由遊びは、それをやっているではないか」とおっしゃった。
苫野さんは、アクティブラーニングを単に協同的な話し合いの場を設ければいいのではないかと受け止められている現状を批判し、
学びの個別化・協同化・プロジェクト化
を新たな教育システムの中核にと主張している。
〇〇スタンダードという流行がある。授業や生活に、そのやり方を示し、順守させれば一定の成果が上がると、教育委員会などが主導している。これは、行政や学校管理には都合がいいだけではないか。多様化の尊重や個に応じた指導などに逆行している。新たな教育システムは、学びの個別化・協同化・プロジェクト化をめざすが、これはスタンダード化を図ることではない。
特別支援教育でも、スタンダードを作っているのではないか。「これなら上手くいく」と考えていないだろうか。
わたしはADHDの指導では、
① 焦点化する。
② 作業化する。プリントを書くなどの作業を多く取り入れる
➂ 見通しを持たせる。どこまでやったら終わりかを明示する、
などでADHD児も集中できると原理化している。これは、それなりの成果があがる。しかし、細かくやり方が決められ、スタンダード化が図られたら、どうなるか。原理は、対象に合わせて変化してこそ、成果が得られる。どこでもだれでもに通用するようなスタンダードなどはあり得ないのではないか。
新たな教育システムの妥当性の検証は、この立ち位置からなされねばならない。そうなってこそ教育改革に向かうことができる。
特別支援教育の推進において、コーディネーターの任命、支援委員会の設置、個別の指導計画の作成などといった施策がとられているが、これらは、どのような原理が働けばよいのかといった検証が必要だと考えている。
苫野氏は「EBPM ( Evidence Based plan Making:証拠に基づいた施策化)には、哲学と教育学のセンス」が必要だとも言っている。
科学が導き出すのはあくまでも仮説的な事実であり、そこから当為(すべし)を直接得ることはできない。哲学は、本質を観取して、その意味を明らかにする。両者の融合が必要だと。
LDのひとの社会自立の力とは何か。どう付き合えばいいのか。吃音でも同じ。そのままで十分社会生活が送れるやり方を手に入れれば、生活が豊かになる。吃音を直すことが全てではない。
公教育の本質とは、「自由の相互承認」の態度を育むこと。自分として、障害は障害として受け止め、生きていくための「力」を育むこと。
これまでの教育はここが曖昧であった。特別支援教育がインクルーシブ教育として進展しているが、自分自身の力を最大限に発揮できる力を育む方向へと学校マネージメントを実施しなければならない。
問われているのは?
① 現代において「自由」に生きるための力とは何か?
② その力はどうすれば育めるのか
③「自由の相互承認」の感度はどうすれば育めるのか?
その一翼を担うのが学びの個別化・協同化・プロジェクト化。探求型の学習である。自分たちなりの問いを立て、自分たちなりの仕方で、自分たちなりの答えにたどり着く。
附属中学校のびわこ学習が、それに相当する。学年を解体してテーマごとにグループを作り、探求型の学習を長年実施している。これは、かって附属中学校のD組の行っていた「生活単元学習びわこ」が原型ではないかと、私はひそかに思っている。
探求型の学習では、教師は、共同研究者である。ある幼稚園で「土に埋めた氷は厚くなる」と言った子がいた。実際に埋めたら氷は溶けていた。その子はみんなから責められ、「なんで?」と先生に訴えた。しかし、担任はすぐに答えを出さなかった。
T「どうしてだろうね。」
CH「前は太くなったのに!」
T「前はどこに埋めたの?」
とヒントを積み重ね、木陰に埋めたことがわかる。いつ掘り返したのか?朝に掘り返した。今と違うよね。先生の問いかけで考えを深めていく子どもたちの姿があった。
デューイの考え方。Learning by doing:為すことで学びが広がる。
テーマに浸りきる。探求テーマに対する問いを立てる。方法を考え、実施。発表する。
[よく遊ぶ子はよく学ぶ子になる]と言われるが、幼稚園の先生たちは、本当に遊びに浸る子は,、小学校に入ってもよく学ぶ子になるのかどうか確信が持てなかった。幼稚園と小中との話し合いが幾度っもたれた。学びは、わくわくすること。探求は最高の遊び。遊びと学習は連続していると考えられるようになった。これが探求型の学習である。
今回のゼミでは苫野氏の論考をもとに、特別支援教育を吟味する二つの切り口が得られた。
一つ目は「望ましい教育システムはなにか」:現在の特別支援教育は,障害のある子もそうでない子もが共に学び合える望ましい教育システムと言えるかどうかを吟味することである。
二つ目は、「新たな教育システムの構築に当たって」吟味すべき課題をとり上げた。次回以降では、この切り口からの考察を進めたいと思っている。
<研究協議>
(1)特別支援教育と通常の教育は融合できるか
中学校の中においては、特別支援学級と通常学級では、あきらかに価値観が違っている。はたして、この両者は、一つの教育システムとして存在できるのか。どのように考えていけばいいのだろうか。
インクルーシブ教育は「包括する」という意味です。特別支援教育を通常教育の中に含めていくという考え方ですね。わたしは、この考え方をもう一歩進めて、特別支援教育が通常教育を包括するものと逆に考えることが、今日的な解釈ではないか。この考えは、支援学級と通常学級が別枠で存在するという教育システムの組織からではなく、特別支援教育の機能(どのような困難さがあろうが、その子の生活や学習を保障していく)から見ていけば、その機能を通常教育にも持ち込まねばならないわけですから、当然通常教育は特別支援教育に包括されねばならないわけです。今はまだまだ通常教育は、特別支援教育機能の圏外にいる。もっと中に収まるように考えていく。現実的には一気にフレネ学校のようにはならないから、部分的に行っていく。成就感、達成感がある教育の体験を増やす。総合的学習を根っこにおいた探求型のプロジェクトを組織して、徐々に広げていく。教科の学習においても、探究型学習をどのように位置づけていくのか、これから考えていくべきではないか。
探求型学習の例として、苫野氏は島根県隠岐の島の島前(どうぜん)高校が、地域課題である過疎化を食い止めるため、全国から生徒が来る高校作りをしていることをとり上げている。これによって、学校も地域も活性化させている。
また、京都の堀川高校は教え込みではなく、大学の研究のような授業をしていた。堀川の奇跡として話題になった。
一方、総合的学習が陳腐になってしまって、形骸化しているところもある。総合的学習にどう取り組むかがわからない教師が出てきて、スタート時は探求型の学習(たんけん・はっけん。ほっとけんが合い言葉だった)であったが、だんだんとないがしろになってしまった。
(2)総合的学習がないがしろにされたのはなぜか
学力を測定可能な基礎学力を中心に検査するようになって、一気に総合的な学習がだめになった。また、総合的な学習は家庭の文化度や家庭の学力がベースになる。この面で優位の子は力を出せるが、ベースが弱い子にとっては総合的学習は何をするのかわからないということから、格差が生じた。しかし、熱心に取り組んできた長野県や岐阜県では、現在もがんばってやっている。
幼児期における遊びは、総合的な学習そのものである。その延長線上で小・中学校の総合的学習をやっていけば、格差は現れないのではないか。探究型の学習をやっていないところで、格差が生じているのではないか。
現在、幼稚園より認定こども園が多くなってきた。そうすると、従来の幼稚園教育が担ってきた自由遊びの中での主体的で対話的な深い学びが、保育園の「預かり保育」に変化してきているのではないか。また、障害のある子どもへの支援加配員がつくようになって、その子の面倒を見る役割になったことから、障害のある子を含む友だち同士の対話的な深い学びがなくなってきている。加配の在り方をもっと論議しないと、幼稚園の統合保育がインクルーシブ教育の在り方の追求に結びつかない。おそれがある。
(3)子ども一人ひとりの深い学びを、どのように見取るか
先日、授業研究会があった。「深い学びをどう仕組むか」が課題であった。理科の授業では、生徒は4人のグループで滑車を転がして、記録用紙を見ながら読み取る力を育てる授業だった。具体物で試行錯誤しながら意見を出し合っていくという流れであった。
このような探求型の学習では、できた子、できなかった子、きっかけのなかった子などに、どのように寄り添っていけばよいのか。「もうちょっとこうやってほしいな」と思う子どももいた。いつも授業中寝ている子が4人のグループでは、少し顔を上げてまとめを書いていた。すごく頑張った姿であったと思うが、全員の中では、評価されなかった。これまでの一斉授業とは違って、探究型の授業では、一人ひとり子どもへの見方をもっていないと授業にならない。一人ひとりの子どもの姿を見ていないと評価できていない。はたしてこの見つめ方を教師がどれだけ持てているのか。
粟津中学校の学び合いの研究協議では、先ほどのような子どもの表情の細かな動きを注目した発言をするように指導され、先生方から子どもの表情についての意見が多く出るようになった。アドバイザーが子どもの表情の見方やその子の学びの読み取り方を示してくれる。そういう存在が必要なのかも知れないと感じる。
幼稚園の先生方は、その子の成長を見守る見方をしている。どのように見守るかは、まだまだ過渡期であり、園の中で調整中である。
通常学級の中の探求型の学習では、どれだけ深い学びをしているのかを的確につかめるかどうかが大きな課題となる。。深い学びは外に現れにくい。長い経過の中で見続けていって、どのような学びを獲得したかを検証しなければならない。前の単元でやっていたことが次の多安元で、このように現れたのかを、実際に体験したことがある。一人一人の子どもが、どのように変わってきたのかが見つめられないと深い学びは捉えられない。その子の知識技能の高まりだけでは、深い学びだったかどうかは判断できないのではないか。
授業参観では、みんな一生懸命やっていると感じたが、これまでの一斉授業の中で身に着けた学習スタイルがどれだけ変化したのか。なにをさして深い学びと言えるのかとなると難しい。
・できあいの答えに到達することではない。
・答えをすぐに言ってほしい子もたくさんいる。
・自分が更なる問いをたくさん持つ子もいる。
・本当に自分が知りたかった内容が明確になった子もいる。
明治以降の教育は、一定の内容を効率的に教えることであった。深い学びというのは、そのような学習内容の効率的な習得ではない
ハーバード大学のサンディ教授の授業をNHKで見たことがある。サンディ教授は、参加者の一人の前の発言を覚えていて、「今の発言との関係はどうであったのか」と指摘している。その参加者に深い学びを意識させようとしている。一斉授業の中でも深い学びを行うこともあったのではないか。
以前、林竹二先生(宮城教育大の学長を務められた方)の授業を見たことがある。これはほとんど子どもたちとのやり取りはなく、大学の講義のようだった。しかし、授業の後で、子どもたちが書いた作文を見ると、一人一人が深い深い学びをしている。林竹二先生は、子ども一人一人の内面に語りかけていたのだ。そうでなければ、あれほどの作文が書けるはずがない。「自分はソクラテスの問答法で授業をやっている」と、先生は述べているが、わたしなどが真似られるものではなかった。子どもの内面をしっかりつかむ方法と技術を身につけねばならない。
(4)今後、深めたい内容
今回のゼミでは、特別支援教育を教育学的に吟味する二つの切り口、
1 どの子にとっても、望ましい教育システムとはなにか
2 新たな教育システムを構築するには
を提言した。
これを受けての研究協議では、
1 特別支援教育と通常の教育は融合できるのか
2 総合的学習がないがしろにされたのはなぜか
3 子ども一人ひとりの深い学びを、どのように見取るか
と、この切り口から深めなければならない内容が提案された。
今後深めたい内容は、これらがベースになると考えている。
1) [特別支援教育の進展過程に見られる通常教育との関連]を、まず明らかにしていきたい。
わたしは、1960年代に小学校の特殊学級の担任した。職場が変わっても、この教育に携わり続けた。一時、養護学校に勤務したが、小中学校特殊学級が組織する県特殊教育研究会の会長を務めるなど、小中学校の特殊教育に関わっていた。
特殊教育は最初、通常学級では学べない異常児の教育して、通常の教育とは別枠で進められた。その後、特殊教育は障害児教育へと進み、特別支援教育の時代を迎えた。この進展過程で、特殊教育は通常の教育とどのように関係していたのか。ここを明らかにすることで、「1 特別支援教育と通常の教育は融合できるのか」に答えられるのではないか。
2)つぎに考察したいのが、「インクルーシブ教育の推進課題」である。
文部科学省は、インクルーシブ教育の推進に当たって、特別支援教育を大きく位置付けている。しかしながら学校現場では、研究協議で指摘された「2 総合的学習がないがしろにされたのはなぜか」を踏まえて、この振興方法を考えねばならない。障害のある子と、そうでない子が共に学ぶインクルーシブ教育では、総合的学習や特別教育活動がその中核を占めねばならないと考えるからである。
3)校内研究・研修の見直し
特別支援教育の教育学的吟味において、これは欠かすことができない課題だと思っている。研究協議で出された、「3 子ども一人ひとりの深い学びを、どのように見取るか」は、校内研究・研修でとり上げねばならない課題である。
また、ここでは、
・ 従来の授業研究を中心とした校内研究でよいのかも検討されねばならない。
・ 個別の指導計画の見直し
日々の実践の中で立案し、実施し教育するのか。今の指導計画では欠陥部分を書き上げ、そこへの指導目標を書くようになっている。自分の長所をどう生かすのか、どう生きるのが一番いいのかを考える指導計画が必要だと思う。自己理解と他者理解する力を育てるにはどうすべきか、などが考察すべき対象になる。
4)最後にLD研で話したように、特別支援教育を中核においた学校マネージメントを究明したい。
文科省のHPを見ると、「共生教育の方向」、「学校の重点目標」、「前年度の学校経営評価をどうするか」などが掲載されている。インクルーシブ教育をどのように進めていくかの学校マネージメントの考察である。
5)今後の展望のために出された意見
〇新学習指導要領は現状の追認をしている。通常学級の中には発達障がい児や、日本語が話せない外国籍の子、義務教育の未終了の子がいる。これらを認めている学習指導要領になっている。そういう子らをまとめてみていく教育でないとやっていけないと考えている。同じ質の子、できあいの答えの教育ではなくなっている。教育のスタンスはかわっている。次の10年後の指導要領では、学年の縛りがゆるくなるだろう。新しい教育システムの構築では、学年の縛りを取っ払う必要がある。
しかし 新学習指導要領が現場では、どれだけ意識されているか。まだまだの状況ではないか。ある市では、いまようやく授業改善が行われ出した。授業研究では、この授業の中に外国籍の子がいる、発達障害の子がいることが話題にはならない。学習指導要領が改正されても、その趣旨を知らないままの人がまだまだ多いのではないか。管理職も学校課題がいっぱいある中で、なにを選択し、なにを伝えるのかハッキリしていない。文科省の考えが浸透するには時間がかかる。
変化には時間がかかるが、インクルーシブの考え方は全世界的な流れである。少しずつ変わっていくのではないか。学年別教科教育にどうしたら特別支援教育が融合できるか。ではなく、特別支援教育をベースにした通常教育を考えないといけない。探求型の学習組織へと学校が変わらないといけないのではないだろうか。
壁になるのは学力テストやいじめの問題である。「友だちを叩いたらいじめである」とはじき出すようなことをしながら、一方ではインクルーシブ教育と言っている。また、学力が足りない人を切り取り、みんなと一緒に学ぶのではなく、個別に教える対象にしている。
以上のような学校現場の状況を踏まえつつ、特別支援教育をベースにした、新しい教育システムの在り方が問われている。
〇いじめや友達同士での激しいやり取りを経験して子どもは成長する。そこが保障されないといけない。現場はまったく進んでいないわけではない。カリキュラムは進んできた。校内のマネージメントも言われて来た。しかし、それらを1本にして、新たな教育システムを構築するという動きにはなっていない。ここにメスを入れねばと思う。
では、これらを重点的にどう取り組めばよいか。学校経営方針。それを立案、協議する方法が学校内で考えられていない。学校が一つのチームとして、切磋琢磨する流れにならない。どの時期からスタートして、年度初めに提示するにはいつから協議するのかなどが大きな課題である。1学期の終わりくらいから来年度の方針を検討している学校がある。わたしは校長の時に、年度末の学校評価の時期に、200字で自分のやりたいことを表現してほしいと、「200字提言」を求めたことがあった。その内容を校務分掌を中心に分担して、考えてもらった。
〇学校評価は、どのようになされているのか。ここにもメスを入れねばならない。中学校で、教科指導だけで校長になった人の中には、支援学級のことを知らなかったり、わからない方がいる。生活単元学習の内容や成長の姿を知らないでいる。わたしは支援学級の担任として、いかに支援学級の素晴らしさを他の先生に伝えるかが使命であると教えられたが、まだまだ知ってもらっていないと感じている。30代の先生、支援学級は経験していない。小中高校にも支援学級がなかった先生もいる。こんなふうにそれぞれの先生には背景があり、その先生の考えが成り立っているわけだから、共通理解をすると言っても、それは大変なことである。
〇「はじめての哲学的思考」の中で、苫野一徳氏は、わが校の教育課題は何かと考えるとき、それぞれの信念がある。信念のレベルで話し合ってもかみ合わない。それぞれの信念はどこから生まれているのかを見つめていかないと議論はかみ合わない。信念の形成には欲望が絡んでいる。その欲望のレベルで議論していけば、なにがベースになってその信念が形成されてきたのかわかり、互いに理解し合える場が得られると述べて居る。このやり方が学校現場は取り入れられるか。
〇点が一つにつながるところが大事ではないか。滋賀県の障害児教育は、同和教育からつながってきたと考えられる。
自由の相互承認。教育はすべての人に自由の相互承認がなされるようにするもの。今はまだ対話が成立しない。相手の言葉を聞く、受け止める。対話と自由の相互承認をどう深めるかから始まるのではないか。
〇通常学級の先生でもきめ細かな指導をしている人がいる。それがそのまま特別支援教育の視点だろう。同和教育でも、子どもを見る視点をもったなら、特別支援教育がベースにならなくても良い。そういう先生がたくさん育つ学校ではいじめや学級崩壊はなくなる。そういう力を育てるにはどうしたらいいのか。良い見方をしている先生から見て学ぶことと巡回相談では伝えている。
〇「本質観取が哲学である」と苫野氏は述べて居る。「教育とはなにか」という問いかけから、「それは子どもの姿に現れてくる」と本質観取したとしよう。そこでは、子ども一人一人がどうやったら豊かな人間関係を作り上げるのかを見つめないと、本質観取にまで行き着いて議論することはできないと思う。
〇大津のいじめへの対応では、どうしてそうなるのかという議論がない。現象面を追いかけている行政の指導であり、それに振り回される学校現場がある。発達障害の子はいじめの標的になりやすい、子どもの価値観が一面的になったときにいじめが起こりやすい、クラスや学校に流れる価値観かも知れない、などのいじめにつながる要因をもっと掘り下げる議論がないと、モグラ叩きしているだけである。インクルーシブ教育が教育の外枠になったらいいのにと思う。
〇教育行政はなにをするのか。それは教育現場の支援者になりきることである。現場が張り切ることをしなければならない。東京都の杉並区ではそういう考えに立って教育行政を進めている。地方教育行政が地方分権の流れのもとに進み、地方独自に解決することになっているが、まだまだ中央集権的な考え方に縋ろうとしている。教育研究所などが中心になって、この地域の今日的課題を掘り起こし、方針を探るなど、各自治体が独自に自分たちの地域の教育を考えていくべきである
あとがき
ゼミの記録に、見出しをつけたり、若干の加除修正を施している中で気づかされたことがあった。それは教育的吟味をしているわたしの立ち位置である。わたしは小学校・中学校の特殊学級の担任であったから、まわりでは通常の教育が進められていた。校内の研究活動や生徒指導などは、通常学級の担任といつも一緒に行なっていた。したがって一つの教育課題に立ち向かうとき、わたしは特殊教育と通常の教育との接点に立たねばならなかった。この立ち位置は、その後、教育研究所や教育委員会に勤務していた時を変わらなかった。教職の最後では小・中学校の校長を勤めたが、特殊教育と通常の教育との接点は「接面」に拡大していた。学校経営を特殊教育の立場から構想するようになっていたからである。
今回のゼミでは、「特別支援教育の教育学的吟味」をテーマとしているが、厳密に言えば、「小・中学校の特別支援教育を通常教育との接面から吟味する」ことになる。このように立ち位置が明らかになることで、焦点化した考察ができるのではないかと思っている。関心のある方は、ぜひゼミに参加し、ご一緒に考察が進められたらと願っています。
次回は11月16日(土曜日)。会場は北脇の自宅マンションの集会室です。
9月の北脇ゼミ
2019年09月03日
虫の音が涼やかにひびく頃となりました。
今日の三日月は中秋の名月へと姿を変えていきそうですね。


今日の三日月は中秋の名月へと姿を変えていきそうですね。


北脇ゼミのお知らせ
2019年06月27日
北脇ゼミのお知らせ
2019年05月02日
北脇ゼミのお知らせ
2018年03月21日
北脇ゼミのお知らせです。
第Ⅵ期・6回は「通級指導教室のセンター的機能 通級指導の役割とは何か」です。涌島真理先生(治田小通級指導教室担任)のお話です。
3/24(土)PM2:00〜4:30
参加費 500円 当日徴収
会場 コミセンやす(学習室2)(野洲駅東口より徒歩5分 野洲市民ホール横)
連絡先 事務局:桂田総司 メールアドレス:kitawakisemi@gmail.com
ご本のお薦め(桂田総司先生より)
新指導要領は授業・学習の大転換を企図!手がかりのご本をヒントに、十分構想をめぐらすべし!
新指導要領『総則』の中で「発達支援」における重点3対象に①発達障がい ②日本語習得の困難 ③不登校を掲げました。加えて『新学習指導要領解説各教科等編』では、各教科等の「学びの過程における困難差への配慮」として、基礎的環境整備した上に、個々の教育ニーズに応じた授業・学習デザインへの転換を求めています。各教科等んおねらいを達成するのに必要な具体的な手だてがそれぞれに明示されています。掲載例示をヒントに、授業と学習の転換を図る段階に入りました。
この3冊はきっとお役に立つことでしょう。新指導要領による転換を意識した内容で見通しが得られ、やる気がわきます。
①『学びを保障する指導と支援−すべての子どもに配慮した学習指導−』ぎょうせい 柘植雅義 2017/12発売
『共生社会の時代の特別支援教育』シリーズ第2巻手にして損なし。新指導要領がめざすインクルーシブ教育の具体像と先行事例記載!
②『教室で使える発達の知識 −発達が凸凹の子ども達への対応−』 クリエイツかもがわ 山田章 2017/11発売
支援の方策・授業/学習デザイン転換の要点が実に面白く記載。発達の視点から教育的ニーズを把握するのに役立つツールが付録化!
③『−発達障がいのある子が育つ− 150の学習課題&学び術』 明治図書 添島康夫 2016/09発売
改訂の目玉は、「自立活動」。通級指導教室での150ものノウハウ・ヒントが「サポート術」と「学び術」で展開。活用が楽しみ。
<第Ⅶ期予告>
第Ⅶ期のゼミは、実践論文の作成を目指すセミナーにすることになりました。
くわしくは、北脇ゼミ事務局までお問い合せください。
第Ⅵ期・6回は「通級指導教室のセンター的機能 通級指導の役割とは何か」です。涌島真理先生(治田小通級指導教室担任)のお話です。
3/24(土)PM2:00〜4:30
参加費 500円 当日徴収
会場 コミセンやす(学習室2)(野洲駅東口より徒歩5分 野洲市民ホール横)
連絡先 事務局:桂田総司 メールアドレス:kitawakisemi@gmail.com
ご本のお薦め(桂田総司先生より)
新指導要領は授業・学習の大転換を企図!手がかりのご本をヒントに、十分構想をめぐらすべし!
新指導要領『総則』の中で「発達支援」における重点3対象に①発達障がい ②日本語習得の困難 ③不登校を掲げました。加えて『新学習指導要領解説各教科等編』では、各教科等の「学びの過程における困難差への配慮」として、基礎的環境整備した上に、個々の教育ニーズに応じた授業・学習デザインへの転換を求めています。各教科等んおねらいを達成するのに必要な具体的な手だてがそれぞれに明示されています。掲載例示をヒントに、授業と学習の転換を図る段階に入りました。
この3冊はきっとお役に立つことでしょう。新指導要領による転換を意識した内容で見通しが得られ、やる気がわきます。
①『学びを保障する指導と支援−すべての子どもに配慮した学習指導−』ぎょうせい 柘植雅義 2017/12発売
『共生社会の時代の特別支援教育』シリーズ第2巻手にして損なし。新指導要領がめざすインクルーシブ教育の具体像と先行事例記載!
②『教室で使える発達の知識 −発達が凸凹の子ども達への対応−』 クリエイツかもがわ 山田章 2017/11発売
支援の方策・授業/学習デザイン転換の要点が実に面白く記載。発達の視点から教育的ニーズを把握するのに役立つツールが付録化!
③『−発達障がいのある子が育つ− 150の学習課題&学び術』 明治図書 添島康夫 2016/09発売
改訂の目玉は、「自立活動」。通級指導教室での150ものノウハウ・ヒントが「サポート術」と「学び術」で展開。活用が楽しみ。
<第Ⅶ期予告>
第Ⅶ期のゼミは、実践論文の作成を目指すセミナーにすることになりました。
くわしくは、北脇ゼミ事務局までお問い合せください。
タグ :通級指導教室
北脇三知也ゼミ
2018年01月21日
私と特別支援教育④ 大学研究室から
特別支援学校 その果たす役割
―地域のセンター的機能― 太田容次さん(ノートルダム女子大准教授)
1/27(土)14:00~16:30
参加費 500円 当日徴収
会場 守山駅前コミュニティーホール(第2ホール)
メールアドレス kitawakisemi@gmail.com
今後の予定 第6回 3/24(土) 「特別支援教育 通級指導教室から」 涌島真理さん(治田小学校通級指導教室)
<ご本のオススメ>
『新しい特別支援教育 ―インクルーシブ教育の今とこれから』 ぎょうせい
『学びを保障する指導と支援 ―すべてのこどもに配慮した学習指導』 ぎょうせい
『連携とコンサルテーション ―多様な子どもを多様な人材で支援する』 ぎょうせい
『共生社会の時代の特別支援教育』シリーズ3冊本。
『パパは脳研究者 ―子どもを育てる脳科学』 株式会社クレヨンハウス 池谷裕二
北脇三知也ゼミ 事務局 桂田総司
特別支援学校 その果たす役割
―地域のセンター的機能― 太田容次さん(ノートルダム女子大准教授)
1/27(土)14:00~16:30
参加費 500円 当日徴収
会場 守山駅前コミュニティーホール(第2ホール)
メールアドレス kitawakisemi@gmail.com
今後の予定 第6回 3/24(土) 「特別支援教育 通級指導教室から」 涌島真理さん(治田小学校通級指導教室)
<ご本のオススメ>
『新しい特別支援教育 ―インクルーシブ教育の今とこれから』 ぎょうせい
『学びを保障する指導と支援 ―すべてのこどもに配慮した学習指導』 ぎょうせい
『連携とコンサルテーション ―多様な子どもを多様な人材で支援する』 ぎょうせい
『共生社会の時代の特別支援教育』シリーズ3冊本。
『パパは脳研究者 ―子どもを育てる脳科学』 株式会社クレヨンハウス 池谷裕二
北脇三知也ゼミ 事務局 桂田総司